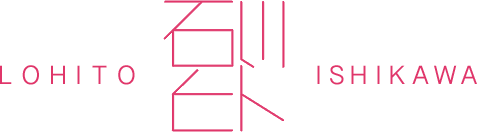2019.01.05
徒歩で国境の先へ。弾丸クレイジー・ジャーニー。高校の同級生と香港スラムに泊まる44歳の旅。

今年になって人生初の海外旅行を経験した高校の同級生S氏から、「今度海外はどこに行く予定?迷惑じゃなければ、次の旅に同行しても良いだろうか?」と、思いがけぬメールが届く。どうやら、遅めの夏休みを1週間ほど消化しなくてはいけないらしく、出来れば近場の海外に行ってみたいという趣旨だった。
大学生ではあるまいし、40を過ぎて毎月アジアをフラフラしている酔狂な輩などそう世界に居るはずもないから、私なんかに声がかかるのはある意味必然というか非常に理に叶っている。何はともあれ「旅バカ」として同級生にも認知されているということは、嬉しいことでもある。
高校の同級生と頻繁に連絡を取りあうことも、最近はさすがに多くは無くなったが、たまたま同時期に別件でもう一人の同級生K社長と何度かメールでやりとりする機会があった。そこで、冗談半分「久々香港に行こうぜ?」と誘ってみたわけなのだが、妻子持ちの40過ぎの男を旅に引っ張り出すことなど海に落としたスマートフォンを引き揚げるのと同じくらい難儀なことと承知していた。ところが、不思議なもので彼から帰ってきた言葉は「ああ、どうしようかな。・・・行けるかなあ。ちょっと確認してみる。」と意外に前向きな返答にこちらが驚いた。
「同級生3人でアジア旅」か...面白いじゃないか。20代も後半にもなれば仕事だ家庭だと普通は難しいことを、40を過ぎた男達には簡単にできるものではない。
翌週、S氏、K社長と私3人の雁首揃えること自体が実に7、8年ぶりという新橋の酒場で「プチ同窓会」が開かれた。皆、新橋の街が随分似合う風体になった。酒の好みも選ぶ店のチョイスもその頃からまた変わったよな、などと語りつつ、妻子持ちのK氏を、いかに上手い具合に籠絡するかを主眼に話をしているうちに、旅の計画はより現実的・具体的なものになって行った。「行っちゃおうぜ。こんなの人生最後かもしれねえよ。」「行っちまおう。」「行っちゃおうか・・・」
かくして、この「クレイジー・ジャーニー」は始まった。
・・・『いっそ、重慶マンションにでも泊まってみるかい?』それは、完全に冗談のつもりで、翌日夜に打ったメールだった。「面白そうだなあ。任せるよ。」いやいや、そこは全否定するべきところを、怖いもの知らずというべきか無謀というべきか、二人は意外と乗り気だ。「東洋の魔窟」「香港唯一のスラム」とも表現される、悪名高きチョンキン・マンションの蔑称とも言うべきその名を並べ、面白おかしく酷い私の宿泊談を話したのだがそれが、かえって逆効果だったか、むしろ途中からこちらが困った。常識的な人間なら、「ホテルはお任せするよ」と言われて友人をまさかそんな貧民窟に泊まらせるわけには行かない。ところが、私も私でそれほど「常識的な人間」でもないから、結論として「まあいいかな。人生一度くらい。」と、正直、私自身も出来れば泊まりたくはないというのに、最終的にはなるのだ。
「OK!後悔しても知らないぜ?」心でそう呟きながら、ビールから日本酒ワインと続いた深夜の酒の勢いも手伝い、旅行サイトで「3部屋2泊分」を予約してしまう。翌朝、眠気覚ましにコーヒーを飲みつつホテルからの予約確認メールが届いたのを見て、軽い後悔に苛まれたことは言うまでもない。まあ。後で恨まれたら、その時はその時だ。
「チョンキン・マンション」というビルをご存知ない方は、是非とも文章の先をご覧になる前に、検索していだきたいと思う。きっと、その方がこの話は多少、面白くはなるだろう。
そんなわけで10月のある日、僕ら高校の同級生3人は、日本の9月くらいに蒸し暑い、夜の帷が下りた香港国際空港に降り立った。
香港のタクシーは大抵日本のタクシーの払い下げだ。以前K社長と香港に来たときには「月島タクシー」というステッカーが室内に残っていて大笑いしたのを思い出す。案の定、どこのタクシー会社の上がりかは知らないがこの大都市に来て赤く塗られた、見慣れたフォルムのトヨタ・コンフォートの車体が、我々の前に滑り込んできた。

チョンキンマンションは、「重慶大厦」と書く。走り出したドライバーに「チョンキンマンション」という言葉が通じないという「まさか」に戸惑う。考えてみれば、「マンション」は英語だ。
「なんて説明すれば分かるんだろうな。ほら、チムサーチョイにあるホテルで、入り口にインド人がいっぱいいて・・・複雑なビルだよ。」と英語で話しながらエアチケットの裏に、漢字で殴り書きをして見せ、そこでようやく話が通じた。
「AH!OK!チョンヂンダーシャー!」と運転手が言った。「チョンチンダーシャ!」「チョンジンダァシャー?」「チョンチンターシャ?」3人で真剣にその発音を真似しているその様子を、ふと、この香港の夜を切り裂くように疾走するタクシーの窓から俯瞰して見たらと想像してみた。きっと学ランを着た湘南のヤンキー高校の教室の窓から見える我々と、二十数年経ったところで大して代わり映えしないような気がして妙にホッとした。やがて遠くに見えてきた摩天楼の光を眺めながらニヤニヤしている助手席の私を、運転手は何か言いたげにチラチラ見ながらも静かに遅いトラックを右に追い越した。
モッコックの西側辺りからジョーダンを抜け、チムサーチョイの街の光を赤いボンネットに輝かせながら、タクシーはやがてその建物の前に止まった。僅かなチップを含めた料金を払い、運転手に手を振ってからビル見上げる。相変わらず、異様な雰囲気の建物だ。荷物を背負い、中に入る。そう。この空気感だ。薄暗いフロアで大勢のインド人に声をかけられながら、宿のフロントへ続くエレベーターを探す。しかし、おかしい。どうも宿の住所に当てはまる棟が見当たらない。チョンキンマンションの内部は、いくつかのブロックに別れた、言うなれば複数の建物が入り組んだような形になっている。向かうフロアによって、乗るエレベーターの場所が違う。警備員らしき初老の男と、通りすがりのインド人にビル入り口の方向を指差し「あっちだ。」と言われ混乱する。K社長が「どうやら、これ、このビルじゃないみたいだな。」と呟いた通り、宿の住所を改めて検索すると「ミラダーマンション」と書かれている。一旦外に出て、地図を見る。チョンキンマンションの2件隣にそのミラダーマンションはあった。チョンキンマンションに輪をかけて妖しげな雰囲気立ち込めるそのビルの入り口に立ち、私は青ざめていた。予約をしたのは間違いなくチョンキンマンションだったはずなのに・・・「別館」あるいは「姉妹ホテル」という位置付けなのだろうか?
同時に、久々のチョンキンマンションを見て、実は大きなカルチャーショックを受けていた。この街の、いわば「アンタッチャブル」の象徴だったあの「魔窟」に。そして、そのワンランク上を行く「ヤバい」このビルに、中高生と思わしき若い子供達がまるで町の映画館にでも遊びに来た風体で、やがて日も変わろうという時間に平然と出入りしているのだ。「俺が親だったら、こんな所には絶対に泊まらせないよ...」そう呟きながら、ミラダーマンションのエレベーターホールの前に立ち、格別人相の悪いインド人と無邪気にスマートフォンをいじる子供に挟まれながら、満員のエレベーターの次を待った。しかし、考えてみれば一昔前までは近づくのも億劫だった大阪は西成、東京では浅草界隈のかつての「簡易宿舎」にも、今や外国人に限らず若者が押し寄せている現状を考えると、これは「時代が変わった」という簡単な言葉で片付けられることなのかもしれない。私にとっては、あるいは、「深夜特急」を読んだ世代にとってこれは、大ショックな出来事なのだけれど。
途方も無い勢いで流れる「アジア」という大河に浮かんだ、我々は「少し古い漂流物」のようなもなのかもしれないと、グラグラと揺れるエレベーターの中で、ふと思った。

混んだエレベーターから吐き出されるようにフロアに着くと、奥の扉に申し訳程度のカウンターがあった。
実は妻子持ちのK社長は、目の前のネイザンロードを挟んだ向こう側、東洋屈指の超高級ホテル「ペニンシュラ香港」に前回は泊まったそうだ。まさに、「天国と地獄」が道路一本を隔てていて、彼はそれを体感することになる。そして、何より「海外旅行初心者」のS氏にはカルチャーショックにちがいない。「申し訳ない」と思いながら意外と手慣れたK社長と共にチェックイン手続きを済ませ、狭く、息苦しく、無茶苦茶な「ヤサ」を見渡しながら、しかし彼らは部屋から出てくると、「あははは、ちょっとこれ見てくれよ!室外機が外じゃなくて廊下に付いてるってどういうこと!?」「すごいよ。俺の部屋なんか、シャワーを浴びるとなぜか部屋の外まで水が流れる設計になってるんだ。」と、暗い顔の私をよそにひたすら笑っているではないか。
「旅」におけるエンターテイメント性というものは、綺麗なビーチや名の通った遺跡ばかりではない。自分の生活の周りに無い「ちょっと普通ではないもの」も楽しみの一つに含まれてくれば、何倍も面白くなる。空港から女性と小綺麗なタクシーで向かう透き通ったビーチとリゾートホテルなど、私にっては正直少し物足りない気持ちになる。変なトラックの荷台に飛び乗って、汗だくになりながらたどり着く、秘境の砂浜の方が、やはりいい。不運やアクシデントを楽しむところまで行けたらそれはもちろん最高なのだが、そこまでいかずとも、多少、ワイルドに旅を楽しむことができる方が、旅も人生も、きっと豊かで幸せに違いない。街に繰り出す下りのエレベーターの中で彼らを見ていて、そんなことをふと考えさせられた。
その晩は、九龍の深夜の街をぶらぶらと歩きながら、初めて入る特段美味くも不味くもないチャイニーズレストランを2件ハシゴしてビールを呑んだ。彼らを連れてゆきたかった屋台街は香港島サイドにあり、そこまで行く時間を考えると空腹には勝てなかった。
「東京より赤道に近いアジアの街で、少なくとも、絶対に裏切らないものは何だと思う?答えはビールだよ。」私の持論だ。高校の仲間で香港に来ているという、あまりにも不思議な現実が高揚感を高め、2本目のビールも、最初の1口目のビールのように美味かった。一人で呑むビールも好きだが、気のおけぬ誰かと暑い街角で楽しく飲むビールというのは、格別だ。
魔窟に戻ると「警備」とは名ばかりの年老いた親父が数人通路に頼りないテーブルを出して、与太話をしながら入り口の番をしていた。形だけの記帳をして先程とは別のエレベーターでフロアへ上がる。どうやら夜と深夜では動くエレベーターが違うらしい。
「明日は、粥を食ってから国境を越えようぜ。パスポート、忘れずに。で・・・大丈夫?一応、ここ2泊分取ってあるけどさ、他のホテルに変えてもいいよ。」
「No problem.」
カッコいいぜ。二人とも・・・心でそう思いながら別れを告げ、我々は暗いビルの廊下を通って、それぞれの「独居房」に消えて行った。まだこの時間、香港島を望む海面には、ギラギラとしたネオンが多少煌いている頃だろう。死にかけの蝉のような室外機の音を少し気にしながら、僕らは不夜城の片隅の、間違いなくペニンシュラホテルのシャワールームより狭いそれぞれの小部屋で、容易く深い眠りに落ちていた。
★
食品関連会社経営のM社長。海外旅行人生2度目の美食家S氏。
共に、いわゆる「ド中国」に上陸するのは初めてだ。しかも、島国日本に生まれ育った我々にとって『徒歩で越境』というのは、かなりエキサイティングなアクティビティである。
喧騒の街で朝粥の朝食を済ませ、中心街から列車に乗って深圳との国境まで行く。現在は「同じ国」に違いないが、このボーダーから先は、通貨が違う、昔ほどではないが人の服装も違う、パトカーも、標識も、匂いも違う。とにかく、街の空気の違いは、誰もが肌で感じるところである。
中国元を握りしめ、越境してすぐのマクドナルドでコーヒーを買い、地下鉄に乗る。深圳のビルの1階にあるディープな屋台風ストリートで、なかなかクオリティの高いネイティブ・グルメをいくつか味わう。これが意外にも美味いのだ。


更には、観光案内に載ってない、超ディープな「新疆ストリート」へと歩を向けた。
5年ほど前の記憶と比べれば恐ろしくこの街は綺麗になっている。しかし、レンタサイクルがなぜか山積みになって放置されている路地や、あまり品が良いとは言えない黄金色の巨大なビルの横には、いかにも昔の中国らしい薄汚れた街並の中国が、街の残滓のように残っている。


私は、彼らにそんな場所を「今のうち」に見せておきたくて、半分廃墟のような塀で囲まれた、貧しそうな小区に少しだけ足を踏み入れた。神様を祀る花やフルーツやろうそく、色鮮やかな何だかわからないものが飾られた小区の入口の門をすり抜ける。塀の内側にやって来た異邦人へ、視線は当然向けられるものの、散歩でもしているうちに道にでも迷ったのだろうという感じで、幸い文句を言われることはなかった。ボロボロの薄汚れたシャツを着た子供たちが私達の横を駆け抜け、老婆は地面に座り一心不乱に何かの作業をしていた。割れた窓、崩れた壁、いびつな地面、上海で聞く普通語とはまるで違う立ち話。いつか近い将来無くなってしまうであろう全てが、今、この場所ならではの魅力的なもののようにも思えた。


30分ほどかけて、ウイグル・ストリートに着く。ストリートと言っても、別に観光客が押し寄せる、西安の「回教ストリート」のような賑やかな場所ではない。言われなければそこがウイグルストリートと呼ばれていることさえ気づかない、低層の建物が立ち並んだ広い道路脇のただの団地群だ。その団地の1階に、ろくな看板も立てない何軒かのウイグル料理屋が入っている。100メートルほど、その団地を歩いてみた。アウディやベンツなどの高級車が団地の裏には並んでいるから、建物はボロくても裕福な暮らしぶりの生活がそこにあることをうかがえる。通りの一番奥まで行き、Uターンしながら『なんか、この店気になるな。』という意見で全員一致した。ワイルドで、地味で、飲食店なのかどうかも分からないような新疆ウイグル料理の店へ、恐る恐る入ってみる。
入り口には、扉すらない。先ほど、ほとんど焚き火に近い釜のようなものの前っで巨大な肉を切ったり、焼けた肉の塊を無造作に外に置かれたステンレスの台へと運んでいた、彫りの深い、いかにも「中央アジア系」の凛々しい目の男が店に入っていった。どうやらここの店員のようだった。
奥の丸テーブルには、すでに2組の先客がいた。表の通りには、食事を求めてすれ違う人などほとんどいなかったのに、やはり我々の嗅覚で「隠れた人気店」を見つける勘が働いたような気がする。
片言の中国語と英語で、ビールと食べ物を注文する。「オススメはなんですか?」さえ通じないのは想像できなかった。「話しているうちになんとかなる」という私の持論がなかなか通らず苦笑いしながらも、なんとか注文を終え、3分後にはちゃんとビールが出て来たので、「多分、7、8割の注文は通ったんじゃないかな?」と笑いつつ、皆で安堵した。
えらく大きな皿がいくつも運ばれてきた。値段を考えると、ずいぶん景気良く盛られているものだ。たった3皿、平均身長180cmの大男3人でも、全部食べきれるか不安になるくらいの量だった。

 いやはや・・・なんということだ。シンプルな新疆料理は何度も中国国内で食べたが、この未体験の本格的料理の旨さに思わず私も驚愕した。焼き方、味付け…これは、日本に居ては絶対に味わえないだろう。そしてこの量。例によって一人旅だったとしたら、1品すら食べきれたかどうか疑問だ。S氏もK社長も、「これは美味いなあ。」「初めての味だ!」とか言いながら羊肉にむしゃぶりついて、それでもやはり全ては食べきれず残してしまった。大雑把な店の作りに反して、ウイグル料理としては、かなりちゃんとしたクオリティの本格レストランだったと言える。それでいて、一人1400円程度。これには驚いた。残念なのがウイグルのビールとウイグルメロンを頂き損ねたということだ。のちに聞いたところによると、あの店の玄関の地面でバッサバッサと雑に切られていたメロンが、実は大変に美味だったらしい。
いやはや・・・なんということだ。シンプルな新疆料理は何度も中国国内で食べたが、この未体験の本格的料理の旨さに思わず私も驚愕した。焼き方、味付け…これは、日本に居ては絶対に味わえないだろう。そしてこの量。例によって一人旅だったとしたら、1品すら食べきれたかどうか疑問だ。S氏もK社長も、「これは美味いなあ。」「初めての味だ!」とか言いながら羊肉にむしゃぶりついて、それでもやはり全ては食べきれず残してしまった。大雑把な店の作りに反して、ウイグル料理としては、かなりちゃんとしたクオリティの本格レストランだったと言える。それでいて、一人1400円程度。これには驚いた。残念なのがウイグルのビールとウイグルメロンを頂き損ねたということだ。のちに聞いたところによると、あの店の玄関の地面でバッサバッサと雑に切られていたメロンが、実は大変に美味だったらしい。

世界は広すぎる。地球に偏在する美味いものや面白い文化は、一生かけても全てを知ることは出来ないだろう。
『「東京には何でもある」とは言うけど、きっと、世界には東京では食えないこういう美味いものが星の数ほどあって、でもそれを知り尽くせないまま、いつか死んでくんだろうな。俺たちは。」』タクシーの中でそう呟いたところ2人に笑われたが、勿論大いに共感はしてくれた。
知らない味を知ることができたからこそ分かること。誰かのインスタグラムの壮大な景色や綺麗な海を見て、景色は結構想像ができる。もちろん、現地でしか体感し得ない臨場感や感動はあるだろう。ただ「食」に関していえば体感を想像することはなかなか困難だ。ものすごい満腹感と、充実感。そして若干の切なさを手に、我々は再び「徒歩」で香港へ戻るボーダーを跨ぐのだった。
★
香港最後の夜は、いつもお世話になってる富豪のFさんと彼のご家族と久々の再会。前日のカジュアル中華の10倍、昼のウイグル料理の20倍くらい値の張るお店で、文句の付けようのない香港料理を色々とご馳走になってしまった。

暫く会わないうちにFさんの娘さんも息子さんも、いつの間にやら恐ろしく美男美女になっていた。この香港で生まれ育ち、昨日、今日と「我々が体験して来たコース」を当然彼らは経験したことは無いだろう。キラキラした家族と同じ丸テーブルに座って、越境して歩いた深圳の街や、ウイグル料理の話。泊まっている酷い宿の話を、M氏が面白おかしく話すのをびっくりしながら聞いているのを見ているのが妙に楽しかった。Fさん自身、何十年もこの街に住んでいるのにあの国境を跨いだことさえないらしい。無論、チョンキンマンションのエレベーターに乗ったことも無い。
「世界が違う」というのは、実に面白いことだ。「ローマの休日」も、「世界が違う」から面白いストーリーになる。カレーを「スプーンで食べる」という一つの日本文化を知らずに育ったらしいFさんに(いわゆるテーブルマナーとして彼はカレーをフォークで食べてきた)、昔、私がいつも「今度会った時は絶対に大船のホルモン焼き屋に連れて行きますから」と誘って嫌がられるという、僕らの「いつものトーク」を、ふと高級デザートをいただきながら懐かしく思い出した。
別れ際、「・・・いつか本当に、大船のホルモン屋のカウンターに座って困惑しているFさんを一度見てみたいよな。」と思いニヤニヤしながら、僕ら3人は中環(セントラル)の雑踏の中に、手を振って消えた。
★

カオルーンに戻るスターフェリーから、黒い海面に滲む香港島の光を眺め、ぼうっと、物思いに耽る10分間こそ、「最も香港的な時間」である。
貧民窟に戻る前に、あのホテルのラウンジでどうしても美味いドライ・マティーニを飲みたかった。S氏は初めてだが、M社長とここに来たのは確か10年位前だ。
オスカー・ピーターソンのピアノを遠くに聴きながら、皆それぞれ、『笑える愚痴』を持ち寄り、『ナッツ』と『180度の夜景』をツマミに、2杯目のマティーニを飲み干した。特に素晴らしいジンやベルモットを使っているわけでは無いとは思うのだが、何故かここのマティーニの味が好きだ。
この街には、天と地、光と陰が常に隣り合わせで混雑している。香港に限らず、その両方を感じ楽しめる旅ほど、濃密で、エキサイティングで、クールな旅はない。
人生は、2度生きられない。
『2度生きるように、世界の『両サイド』を旅出来ることこそ、本当の贅沢じゃないだろうか。』そう言ってみた。
…8割は本心、2割程度は負け惜しみか?
魔窟の狭いエレベーターを昇り、ビルの住人の洗濯物のカーテンの下をくぐり、そのエレベーターより申し訳程度に広い部屋の天井を見上げているうちに、柔らかい睡魔が訪れる。
昼に食べた料理のせいだろう。ウイグルの草原に佇んだ、顔の黒い羊の夢を見た。
『君が見上げるシルクロードの星空は、香港島の夜景より、本当に綺麗なのかい?』
その答えを聴く前に、俺は九龍の夜よりも深い漆黒の眠りに落ちていた。
『高校の同級生と香港スラムに泊まる44歳の旅。』
終