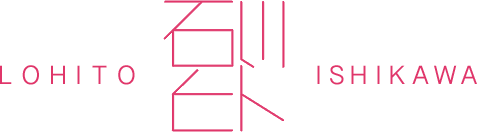2016.10.28
名も知らぬ茶人の水指。

それは、遠い島から漂れ着いた流木のように、
かつての持ち主の素性を明かさぬまま、現代流通という大海原を漂いながら
その器は自分の手元に渡ってきた。
多くのマーケットに流通する「茶道具」や「骨董」の多くが、
そうした過去の持ち主という記憶を消し去り、次の商人や茶人、趣味人の手に渡るのだ。
茶道具である「水指」として手に入れたこの器は、
いわゆる典型的な水指の型と比べればかなり風変りである。
フォルム的には、深さが無く口が開いている。
明らかに、本来の寸胴型か、或いはそれに近い縦横比ではない。
もちろん世にそういう水差しの類も無くはないのだが、
茶人が見れば誰もが、良くも悪くも「おや。これは?」
と思うくらいの印象を受ける形状なのだ。
埃を纏った、古びた共箱の筆文字を見てその形に「そうか。なるほど。」と思う。

箱書きに「菓子鉢」の文字。そう。この水指は、元々は菓子器として作られたものなのだ。
どこぞの名もなき茶人が、
この器にどれほど愛着を持っていたのか、眺めれば眺めるほどほどそれを深く感じる。
散り散りに割れた菓子器のカケラを寄せ集め、確かな仕事の職人に託した丁寧な漆継ぎ。
「金継ぎ」では幾分派手すぎてしまう。けれど朱漆だけでは少々寂しい気持ちもする。
そこで、欠片ごと失われた場所に、金と銀で美しい桜の花びらをあしらう。
銀は酸化で今でこそ灰色となっているが、
それが朱漆とのコントラストとして実に品の良い侘しさを醸している。
何と言うセンスだろう。
変な話だが、私はこの器を見て、古代エジプトの王の墓のミイラを連想した。
古代エジプトでは、来世への復活信仰により王の魂を蘇らせたい一心で、
大変に手の込んだ丁寧なミイラが作られた。
こよなく愛した菓子器が割れ、ただの陶片になってしまったことを憂い、
どうにかしてこれを美しいものに蘇らせることは出来ないだろうかというその想いが、
この風変わりでありながらも何とも言えぬ美しい水指として、今、この佇まいを残しているのだ。

茶道具の「格」としては残念ながら、ここまで大きく割れてしまえば、
価値は相当に落ちることだろう。けれど、それが何だ、と私は思うのだ。
茶の世界は、どこぞの偉い御方が箱に筆を走らせれば、その器の市場評価価値は何倍にも上がる。
代々継がれる陶芸の名門で、必ずしもまだ修練と技術が伴わない、
「本物」と名のついた桐箱入りの茶碗は、人々に大変珍重され続けてきた。
それが必ずしも悪いとは言わない。
勿論良いものは良いわけだし、そういう価値体系あるからこそ、
伝統は育まれ、日本の素晴らしい道具の世界は、広い裾野を保ちつつ永く続いてゆくからだ。
一番の問題は、我々がその金銭的尺度だけでモノを見てしまった場合、
作品を、見たり愛でる感性が、ただただ失われる一方ということだ。
名もなき陶芸家が作った見事な器や、共箱(作者が箱書きしたもの)が無い為に、
かつての名工が作った見事な作行の器が、まるで無価値のように考えられてしまうようなことだ。
陶芸の世界は奥があまりにも深い。
けれど、器の作り手ばかりか、使った人の想いが乗った道具の美しさやロマンを感じられる、
世俗的価値とは少し違うベクトルの「良いもの」に偶然出会った瞬間、
そこには「良いモノ」好きならではの、何とも言えぬ価値感と感動が生まれるのだ。